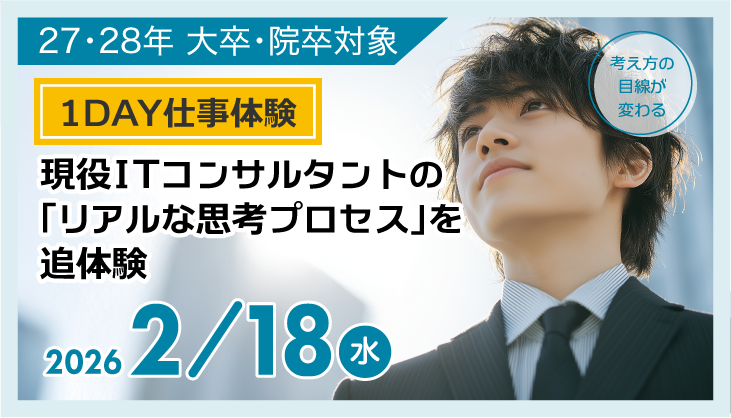コンセプト経営

日本の外車の輸入台数は、おおよそ30万台で推移しています。輸入台数トップがメルセデス・ベンツで次がフォルクスワーゲン、三番目がBMWです。もっともフォルクスワーゲンはディーゼルエンジンのデータねつ造事件の影響で、2016年の登録台数は、BMWの後塵を拝する結果に終わっています。登録台数総数が280万台でそのうち輸入車が約10%を占めています。ヨーロッパ車は、ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ジャガー、ポルシェ、フェラーリなどいずれも個性的で魅力あふれる存在です。車好きには憧れのモデルのショールーム状態です。
メーカーごとに個性的なコンセプトでまとめられた商品を展開するというビジネススタイルは、世界最大の車市場であるアメリカでも日本でもあまり見受けません。アメリカや日本のメーカーは、車種ごとに売れそうなコンセプトで車をまとめ上げていくスタイルを取っています。こういうスタイルの場合は、商品のラインナップからは企業の特徴を示すコンセプトははっきりしません。A社の車がB社で売られていても気付きません。実際、同じ車を車名だけを変えて販売されているケースも多々あります。同じことをヨーロッパのメーカーがやったらバレバレです。BMWの車をベンツの商品として売るなんてことになるわけですから。
こうした二通りのビジネススタイルはどちらが勝っているのでしょうか?あるいは、ビジネスの上でそれぞれどんな得失を有するのでしょうか?考えてみたいと思いますがなかなか難しいですね。ベンツやBMWのように個性的なコンセプトで統一した商品ラインナップでビジネスを展開する場合には、その個性的な唯一のコンセプトを継続的に引継ぎ高めていくことで、その商品群のグレードは年々高められ益々魅力的なものになっていきます。エクステリア、インテリアのデザインは、そのデザインのイメージ、魅力が継続的に継承され、そのデザインの品質は高まっていきます。エンジンについても同様にその動力特性、低速で力強いか、高速域で伸びが良いか、あるいは中速域での力強さを持たせるのかといったことやエンジンの排気音にもそのメーカーらしいサウンドが継続され、開発者はモデルに依らず伝統的なコンセプトに従って品質を高めていくことが、開発の基本的な姿勢になります。こうしたビジネスモデルの優位な点としては、商品コンセプトや、品質基準の理解が浸透し、製品づくりや販売の現場までより昇華され、そのブランドは魅力的なものとして競争力を増していきます。これがヨーロッパ車の魅力の源泉でしょうか。
色とりどりのチューリップが賑やかです。昨年の秋に愛妻が仕込んだ100本のチューリップです。何事も先を読んで策を練って行かねばなりません。
2017年5月1日